01 理系な人々、文系な人々
更新日:2025年3月6日
ティーンのためのAichi Librarians' Choice
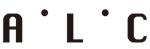 あるく
あるく
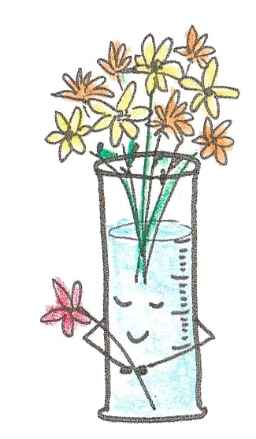
愛知県内の図書館員が、ティーンのみんなにオススメの本を紹介するよ!第6号のテーマは「理系!vs 文系!」
編集:愛知県公立図書館長協議会ヤングアダルトサービス連絡会
PDFファイルはこちらから→A・L・C あるく 第6号(冊子印刷用)
01 理系な人々、文系な人々
![]() 『世界を変えた50人の女性科学者たち』 レイチェル・イグノトフスキー/著,野中 モモ/訳 創元社 2018.4
『世界を変えた50人の女性科学者たち』 レイチェル・イグノトフスキー/著,野中 モモ/訳 創元社 2018.4
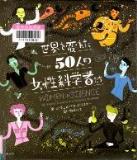
ヒュパティア、ハーダ・エアトン……みなさんはその名を知っていますか? 彼女たちは科学や数学で大きな功績を残した人たちです。しかし、恥ずかしながら私はこの本を読んで、はじめて彼女たちを知りました。私みたいな人も多いのではと思います。なぜなら、彼女たちはどんなにすばらしい研究をしても女性だという理由で学問の世界からしめだされ、存在を認められなかったからです。
しかし、彼女たちは諦めなかった。周りの反対や逆境に負けず、努力を続けてきました。そんな先人たちの姿勢は、これからを生きる私たちに夢と勇気を与えてくれます。
(豊橋市中央図書館 ぴーす)
![]() 『朝永振一郎 見える光、見えない光』 朝永 振一郎/著 平凡社 2016.10
『朝永振一郎 見える光、見えない光』 朝永 振一郎/著 平凡社 2016.10

日本人として二人目にノーベル賞(物理学賞)を受賞した朝永(トモナガ、と読みます)さんは、偉大な功績とは反対に、いつも人生に迷っています。学生時代に早くも「田舎で余生を送りたい」と思い、研究所で働き出してからも「自分のようなものはいてもいなくても」と悩む。挙句の果てには自分は物理が「それほど好きそうでもないようだ」という衝撃の告白! 朝永さんの人間臭いエッセイを読んでいると、物理という学問にぐっと親しみがわきます。
(名古屋市鶴舞中央図書館 石谷睦美)
![]() 『バッタを倒しにアフリカへ』 前野ウルド浩太郎/著 光文社 2017.5
『バッタを倒しにアフリカへ』 前野ウルド浩太郎/著 光文社 2017.5

妙な題名、妙な表紙の写真、そして妙な著者名(ごめんなさいちゃんと理由があるのです)。そんな奇妙な第一印象の本でしたが、熱量の高さに引き込まれました。印象的なのは、歩む道の過酷さもなんのその、自分の昔からの「好き」をどこまでも追うその姿。正直今の社会で(理系に限ったことではありませんが)好きな研究を続けていくのは大変なことです。「現実を見て考えよう」と言いつつ、それでも「好き」を追い続けるならそっと手渡したい本です。
(名古屋市守山図書館 弓)
![]() 『深海の女王がゆく 水深一〇〇〇メートルに見たもうひとつの地球』 シルビア・アール/著,伯耆 友子/訳 日経ナショナルジオグラフィック社 2010.7
『深海の女王がゆく 水深一〇〇〇メートルに見たもうひとつの地球』 シルビア・アール/著,伯耆 友子/訳 日経ナショナルジオグラフィック社 2010.7
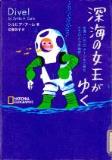
地球の7割を占める海。その面積は3億3,000万平方キロメートルに及ぶが、これまで人類が探検できたのは、そのうちの5%にすぎない。
謎と不思議に溢れた海にいかに魅せられ、海洋探検家・海洋学者となったのか。そして、いま地球が抱える危機とはどんなものなのか。海についてのQ&Aを含め、アメリカ大統領や、ロシア首相ともわたり合う「深海の女王陛下」の異名を持つ著者が、自らの経験を交えて語る。
(碧南市民図書館 まる。)
![]() 『ざんねんな日本史偉人伝』 NHK『DJ日本史』制作班/協力 宝島社 2018.7
『ざんねんな日本史偉人伝』 NHK『DJ日本史』制作班/協力 宝島社 2018.7
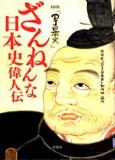
あなたの好きな日本の偉人は誰ですか? 憧れの偉人には、実はとっても残念なエピソードがあるかもしれません! 『戦国』 『江戸・幕末』 『古代・中世・近現代』の選りすぐりの44人を、イラストをまじえて楽しく紹介。「それでも憎めない」、「逆に好きになった」、「がっくりした」。 あなたはどんな感想になるでしょうか? ショックを受けた人、ごめんなさい!! 偉人達は皆個性的だったのです。あきれながらも結構歴史の勉強になりますよ。
(あま市美和図書館 あめちゃん)
![]() 『文豪たちの友情』 石井 千湖/著 立東舎 2018.4
『文豪たちの友情』 石井 千湖/著 立東舎 2018.4

性格の烈しい人が多い文豪。そんな文豪たちの友情はとても熱い! 寝る時間以外はいつも一緒だったから男色関係を疑われた佐藤春夫と堀口大學、川端康成を新婚旅行に同伴させようとした横光利一など全13組の文豪たちの友情が紹介されています。自我の強い人が多いので、ケンカや論争も激しく面倒くさいことも多いのですが、お互いを尊敬しあい高めあう友を持てた彼らが羨ましく思えます。
(碧南市民図書館中部分館 ゆり)
![]() 『美坊主図鑑 お寺に行こう、お坊さんを愛でよう』 日本美坊主愛好会/著 廣済堂出版 2012.2
『美坊主図鑑 お寺に行こう、お坊さんを愛でよう』 日本美坊主愛好会/著 廣済堂出版 2012.2

みなさんはパワースポットに足を運ぶことはありますか? 全国にはさまざまな種類のパワースポットがありますが、「お坊さんに会いに行く」ためにお寺を訪れてみるのはどうでしょう。この本を読んでみると、お坊さんやお寺に対して親近感が沸いてきます。中にはイケメンなお坊さんもいたり…?!
どんなきっかけでも、古くからの文化に触れることは素敵なことだと思います。ぜひ、自分なりの日本文化の楽しみ方を見つけてみてください。
(岡崎市立中央図書館 落花生1号)

